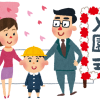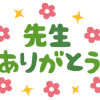子どもの保育園入園が決まると、いよいよあなたの仕事復帰も近づいてきますね。
仕事先の人に、「いつから仕事に来れる?」と聞かれることもあるでしょう。
そんな時、絶対に忘れてはいけないのが、慣らし保育!
実は、保育園の入園が決まっても、初日から丸々1日預かってもらえるわけではありません。
子どもが保育園に慣れるまで、保育時間を短縮する『慣らし保育』の期間があるんです!
何も知らずに入園初日から1日預かってもらえると思い込んでいた私は大混乱。
- 慣らし保育って一体何なの!?
- いつまで慣らし保育が必要なの?
- 慣らし保育はどうやって進めるの?
- 仕事はどうしたらいいの?
こんな疑問で頭が真っ白になった経験があります。
もしかしてこれを読んでいるあなたも、慣らし保育のことがよく分からずに悩んでいるのではないでしょうか。
分からないことは先生に聞くのが1番…とは分かっていても、そもそも何から質問すればいいか分からないし、先生も忙しそうだし…なーんて躊躇しちゃいますよね。
そんなお気持ち、よく分かります。
そこで今回は、慣らし保育の期間や、一般的な慣らし保育のスケージュールを詳しくまとめてみました。
これを読めば、慣らし保育の予備知識はバッチリです!
まずは「慣らし保育とは何なのか」を、さっそく見ていきましょう!
スポンサーリンク
そもそも慣らし保育とは一体なに?
慣らし保育とは、入園する子どもが、保育園という新しい環境に段階的に慣れていくための、いわば『練習期間』のようなもの。
入園初日からいきなり1日保育園で過ごすのではなく、初日は2時間でお迎え、2日目は半日…というように、少しずつ保育時間を延ばしていくのが基本的な慣らし保育のやり方です。
でも、どうせこれから毎日保育園に通うのに、慣らし保育なんて本当に必要なの?
初日から1日預けた方が、早く慣れるんじゃない?
そんな風にも感じてしまいますよね。
しかし!実は、慣らし保育をすることにより、子どもだけでなく親や先生にとっても大きなメリットがあるんですよ!
それでは、慣らし保育の必要性を具体的に見ていきましょう。

子どもにとってのメリット
親と離れることに慣れる
初めて保育園に通う子どもにとって、1番の不安はママと離れること。
ある日突然、長時間ママと離れることになるのは子どもにとって負担が大きいものです。
そこで、慣らし保育により少しずつママと離れる時間を延ばしていくことで、不安感やストレスを軽減することができます。
先生や友達に慣れる
保育園は、初めて会う先生・友達で溢れています。
知らない人ばかりの環境でいきなり1日を過ごすことは大人でもストレスになりますよね。
慣らし保育では、少しずつ先生や友達と接する時間を増やすことで、段々と先生や友達の顔を覚え、無理なく馴染んでいくことができます。
保育室に慣れる
室内の環境も、家と保育室では大きく違います。
見慣れない机やロッカーに、戸惑うことでしょう。
慣らし保育は、こうした室内の環境に徐々に慣れていくという目的もあります。
一気に環境を変えることは子どもにとって負担になってしまうことがあるので、慣らし保育によって少しずつ慣れていくのがベストです。
集団生活に慣れる
保育園入園は、子どもにとって初めての集団生活でもあります。
慣らし保育によって、少しずつ集団生活を体験することで、初めての集団生活への不安感を軽くすることができます。
生活リズムが整う
保育園に通うようになると、ママも仕事が始まり、ある程度決まった時間の中で行動しないといけなくなります。
今までより朝早く起きなければならなくなったり、お昼寝の時間が決まっていたり…と、新しい生活リズムへ移行させる必要があります。
慣らし保育では、こうした生活リズムの調整を、少しずつ無理なく行うことができます。
親にとってのメリット
実際の園の様子を知ることができる
慣らし保育は、入園前の見学だけでは分からなかった園の様子や雰囲気を知る良い機会です。慣らし保育の場合、最初だけ保育室まで保護者が付き添ったりしますので、そうした機会に室内の様子を見ることができます。
普段の様子を見ることで、安心感をもって子どもを預けることができるでしょう。
先生達とコミュニュケーションが取れる
慣らし保育の期間は、担任の先生と密にコミュニュケーションを取る絶好のチャンスです。
本格的に仕事が始まる前に、不安なことや気になることを先生に伝えておくと安心して仕事がスタートできます。
通勤時間等の把握ができる
慣らし保育を行うことで、本格的に仕事がスタートした時のシュミレーションができます。
家から保育園までどれくらいかかるのか、何時に保育園に送れば仕事に間に合うのかを、慣らし保育で確認できるので安心です。
先生にとってのメリット
子どもの性格を知ることができる
慣らし保育の期間があることによって、先生もゆっくりとその子どもの性格を知ることができます。
初めてお預かりする子どもですから、手探りなのは先生も同じ。
慣らし保育で時間をかけてゆっくり向き合うことで、どんな接し方をするのが良いのかを見極めることができます。
保護者と密にコミュニュケーションを取ることができる
慣らし保育中は保護者とのやりとりが多くなるので、保護者がどんなことを望んでいるのか、どんなことを心配しているのかなどを把握する良い機会となります。
慣らし保育の期間を使って、子どものことだけでなくその保護者のことを知り、ニーズに合った保育を行うことができます。
慣らし保育には、こんなに多くのメリットがあるんですよ!
子どもはもちろんのこと、親や先生にとっても、慣らし保育は大切なこと。
これから始まる園生活を充実させるためにも、ぜひ慣らし保育はしっかりと行いたいですね。
一方で、ちょっと気がかりなのが慣らし保育の期間…。
これから仕事を始めるあなたにとっては、保育時間の短い慣らし保育がどれくらい続くのか、気になりますよね。
それでは続いて、慣らし保育は一体いつからいつまでなのか、その期間を見ていきましょう!
スポンサーリンク
慣らし保育の期間はいつまで?
慣らし保育は、基本的に入園初日から始まります。そして、いつまで続くかというと、平均1週間〜2週間です。
え?平均?そんなにアバウトじゃなくてもっとハッキリした日数を教えてよ〜!
そんな声が聞こえてきそうですが、実は、慣らし保育の期間は「必ず○日やって下さい」等の決まりはありません。
どれくらいの時間をかけて慣らし保育を行うかは、その保育園の方針次第、ということになります。
また、平均1週間〜2週間というのは、順調に慣らし保育が進んだ場合の日数です。
…じゃあ順調に進まないこともあるのか?というと、はい、残念ながらあります…。
例えば、
- 入園初日から子どもが風邪をひいてほとんど登園できなかった!
- 思った以上に保育園を嫌がってなかなか慣れない…
こんな場合には、慣らし保育の期間が延びてしまう可能性大です!
かくいう私の娘も、入園初日に保育園の洗礼とも言える風邪をもらってきてしまい、結局最初の1週間は保育園をお休みすることに。
それからようやく慣らし保育が始まったので、保育園に丸一日通えるようになったのは予定よりも1週間遅れでした。
仕事も、急きょ無理を言って時短勤務にしてもらい、職場にご迷惑をおかけする事態となりました(;´Д`)
また、園によっては、慣らし保育の初日〜数日は、お母さんも同伴してくださいとお願いされることもあります。
そうなれば、時短勤務どころか数日仕事を休まなればなりません。
こんなこともありますから、慣らし保育を始める前に、次の4つのことをやっておきましょう!
- 事前に園に慣らし保育の期間を確認する
- どれくらいの期間で慣らし保育を終えたいのか、園に要望を伝える
- 職場に慣らし保育があることを伝え、仕事を調整する
- 慣らし保育が長引くこともある旨を伝え、理解を得ておく
慣らし保育は基本的に入園初日からです。
しかし、園によっては、入園日より1週間〜2週間前に『一時保育』という扱いで慣らし保育を行い、入園初日から仕事が開始できるようにしてくれる園もあります。
また、「○日までに慣らし保育を終えたい」と希望を伝えておくと、できるだけその期間で慣らし保育が完了するように調節してくれる園もあります。
まだ慣らし保育の期間を相談していなければ、仕事の日程も含めて早めに園に確認をしてみてくださいね!
スポンサーリンク
慣らし保育のスケージュール
慣らし保育の期間を詳しく見てきましたが、では、1週間〜2週間かけてどのように慣らし保育が行われるのでしょうか?
なんだかまだ、慣らし保育の具体的な進み方がイメージできない…
そんなあなたのために、慣らし保育のスケージュール例を挙げてみました!
今回は、よくあるパターンの慣らし保育と、親同伴で行われる慣らし保育のスケージュールをご紹介しますので参考にしてみてくださいね♪

こんな感じで慣らし保育は進んでいきます。
慣らし保育の進め方は園によって異なりますので、必ずしも上記のスケージュールになるとは限りませんが、このような日程を組む保育園は多いです。
こうして見ると、けっこう慎重だな〜なんて思ってしまいますよね。でも、最初にお話したことを思い出してください!
この期間があることで、安心して保育園に通うことができるのです。
あまり焦らずに、気持ちに余裕を持って進めていきましょう。
どうしても仕事を休めないときは?
スケージュールを見て分かる通り、慣らし保育の期間はお迎えがかなり早めです。
できるだけしっかり慣らし保育をしてあげたい、でも、こんなに毎日早いお迎えはムリ!
そんな場合には、まず保育園に、慣らし保育を早めに終えたい旨を伝えましょう。
先にもお話したように、ママの仕事の都合に合わせて慣らし保育をペースアップしてくれる場合もあるからです。
しかし、あまりにも子どもが慣れていないなどの理由から、慣らし保育の期間は変えられないということであれば、お迎えを代わってもらうことも考えましょう。
祖父母など頼れる人がいない場合には、ファミリーサポートセンター事業(通称ファミサポ)を利用するのもひとつの方法です。
市役所に問い合わせ、事前に会員登録・打ち合わせをすると、ママがお迎えに行けない時に、担当会員が代わりにお迎えに行ってくれます。
慣らし保育期間中は、極力ママがお迎えに行くのがベストですが、どうしてもという場合には利用を検討してみてくださいね。
スポンサーリンク
なかなか慣れない時はどうする?
慣らし保育の進み方が分かったらからもう大丈夫!…と、安心するのはまだ早いかもしれません。
実は、慣らし保育で多くのママが1番頭を悩ませるのは、スケージュールでも仕事の都合でもなく、スバリ、慣れないこと。
子どもに合わせてゆっくりと進めているつもりなのに、全く保育園に慣れてくれない…。
保育園の駐車場に着いただけでギャン泣き!これじゃあ仕事が始められない〜!
こんな経験をしているママはとっても多いんです!
これから慣らし保育を迎えるあなたも、もしかしたら慣らし保育が進まないことに頭を悩ませるかもしれません。
そこで最後に、慣らし保育がうまく進まないときの対処法をご紹介したいと思います。
さっそくチェックしていきましょう!

焦らない・比べない
1番はコレ、焦らないこと、そして、人と比べないこと!
子どもがなかなか保育園に慣れてくれないと、焦ってしまいますよね。
○○ちゃんはもっと早く慣れたのに…なんて、他の子どもと比べてしまうこともあるかもしれません。
しかし、こういった焦りは1番NG!
あなたの焦りは表情や雰囲気ですぐに子どもに伝わります。
あなたの心が穏やかでないと、子どもは不安になり、余計に保育園を嫌がってしまいます。
なかなか保育園に慣れなくても、「みんなこんなもん!」「いつか慣れればいいや!」と、前向きに考えて気持ちを落ち着けましょう。
サッと離れる
保育室の入り口で、「ママ〜!」と泣き叫ぶ我が子。
そんな姿を見ると、後ろ髪を引かれる思いでなかなかその場を離れられませんよね。
しかし、これもNG!
泣いているからといって、いつまでもそばにいては子どもも切り替えができません。
離れるときに泣いてしまう場合は、「ちゃんとお迎えに来るからね」と目を見て伝えたあと、サッとその場を離れましょう。
案外子どもは状況を分かっているもので、ママが行ってしまうと諦めてケロッと遊び始めることもあるんですよ。
安心する物を持たせる
お家でいつも使っている毛布や、ママの匂いのするハンカチなどを持たせてあげるのもひとつの方法です。
おもちゃはお友達とのトラブルの原因になるので保育園には基本的に持ち込めませんが、毛布やハンカチであれば許可してくれる保育園も多いです。
先生に相談の上で、そうしたものを活用するのも良いでしょう。
ごめんねよりありがとう
泣きながら保育園に行く我が子を見ると、なんだか申し訳ない気持ちになってしまうと思います。
私も、慣らし保育の時はなんだか子どもに悪いことをしているような気持ちになって、家に帰ってからごめんね…と娘に謝ってしまうことがありました。
でも、これは余計に子どもを不安にさせるためNG。
ごめんねではなく、頑張ってくれてありがとう!と伝えてあげてください。
まだ言葉を話せない子どもでも、言っていることはよく理解しているものです。
できるだけ多く、前向きな言葉をかけてあげましょう。
このようなちょっとした工夫・配慮をするだけで、翌日から急に泣かずに登園できるようになることもあります。
なかなか慣らし保育が進まない時は、こんなことに気をつけてみてくださいね。

まとめ
いかがでしたか?慣らし保育の期間や進め方をまとめてきましたが、参考にしていただけたでしょうか。
慣らし保育って大変なんだなぁ、と不安に感じたかもしれませんが、もちろん、保育園の先生たちもたくさんサポートしてくれます。
分からないこと、不安なことは、どんどん先生に質問すると良いでしょう。
慣らし保育は、これから始まる園生活を楽しくするための大切な期間。
焦らずに、前向きな気持ちで進めていってくださいね!